水谷 聡(みずたに さとし)
大阪公立大学 大学院工学研究科 准教授(愛知県出身)
(2025/4/30掲載)
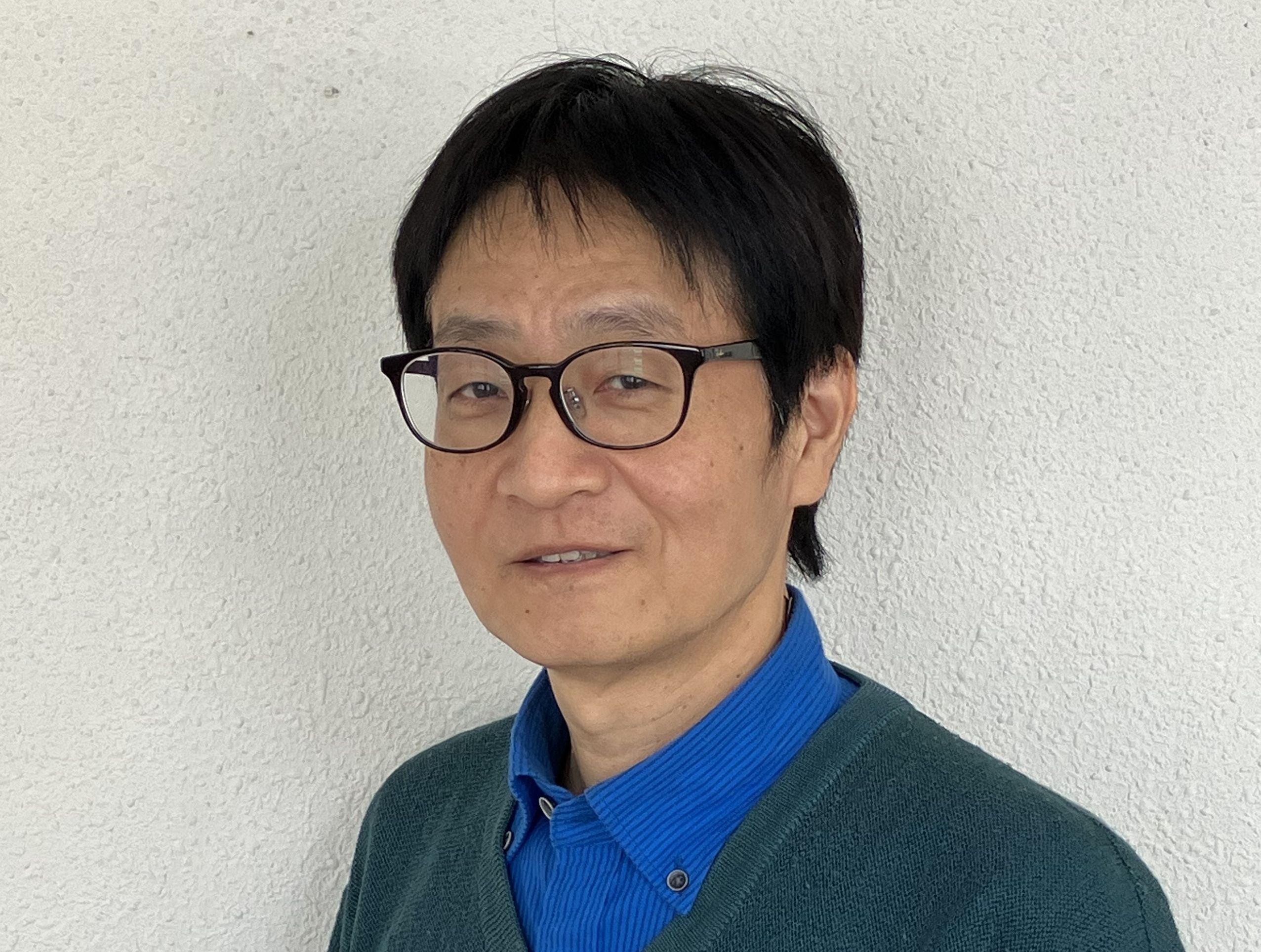
災害廃棄物に関わったきっかけ
京都での博士課程の学生時代に阪神淡路大震災が起こりました。当時、災害廃棄物についてはほとんど何も情報がない中、高月紘先生、酒井伸一先生のご指導の下、震災時の家庭系ごみの組成調査や、解体工事のトラックに同乗させてもらいながら、倒壊建物の廃棄物発生原単位の推定などを行ったのが、災害廃棄物に関わった最初です。
もっとも強く印象に残ったこと
研究室の後輩の実家が倒壊し、貴重品などを取り出しに行ったのは重たい思い出になっています。高速道路の高架が倒れたり、大きな建物が倒壊したりするなど、ヒトが作ったモノがいとも簡単に壊れることや、身の回りのモノが総て廃棄物予備軍であることなども思い知らされました。また、神戸市長田区では大規模な火災が発生しましたが、研究室が大学の化学物質管理に関わっていたこともあり、災害時の化学物質管理の重要性を意識するようにもなりました。
現在の災害廃棄物対策との関わりや今後取り組みたいこと
災害時の化学物質の漏洩対策や漏洩リスクに対して、PRTR制度を活用するに当たっての課題と改善方法について検討しています。一般的にはPRTR制度によって化学物質の存在場所や存在量が正確に把握できるように思われていますが、そもそも災害時を意識した制度ではないため、災害時に役立つ化学物質管理制度が必要であると感じています。
災害廃棄物対策に関して欲しい情報、共有したい情報
普段はほとんど意識されませんが、身近な事業所などでも、有害性の高い化学物質が大量に使用・保管されています。災害廃棄物処理計画や防災計画を作る際や、実際に災害が起きた時に、それらのリスクが的確に把握できるような情報や仕組みが必要だと感じています。
その他、災害廃棄物対策に関する思いなど
阪神大震災に遭遇したとき、私が生きている間には、こんな規模の地震はもう起こらないだろうと感じたのですが、残念ながら、同じような災害がいつ起きても不思議ではない状況になりました。災害廃棄物対策も当時と比べれば遙かに進みましたが、それは私たちが多くの災害に見舞われてきた証でもあります。災害廃棄物への備えが不要となることを願いつつ、災害が起きたときには有効である対策づくりに微力ながら貢献できればと思います。